TSMCの熊本第2工場計画の現状と影響

これまで熊本県内企業による半導体関連の進出については、複数のレポートを通じて事実や動向を整理してきました。
本回は、世界最大の半導体受託生産企業である台湾積体電路製造(TSMC)が、日本で2番目の半導体工場を熊本県に建設する計画について、その進捗状況、報道の背景、そして地域経済・社会・環境への影響を多角的な視点から捉えるコラムとしてお届けします。これまでのレポートとは異なり、少し柔軟な視点で地域の変化を見つめます。
※TSMCは、2025年10月16日の第3四半期決算会見で「日本での第2工場の建設は既に開始している」と明らかにしました。
情報戦で周りと差をつけるならWEB会員がおすすめ!
当研究所は設立から35年以上、自信を持って熊本の時事ネタ・最新経済情報をお届けしています。
TSMC熊本第2工場の概要

TSMCの熊本第2工場は、熊本県菊陽町の第1工場の隣接地に、年内の着工を目指して計画が進められています。
運営主体は、TSMC、ソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社、株式会社デンソーに加え、第2工場建設に合わせて新たに参画したトヨタ自動車株式会社が共同出資する子会社「Japan Advanced Semiconductor Manufacturing株式会社」(JASM)です。
JASMの出資比率は、TSMCが約86.5%と過半数を占め、ソニーセミコンダクタソリューションズが約6.0%、デンソーが約5.5%、トヨタが約2.0%となっています。この構成は単なる資金提供にとどまらず、戦略的な意味合いを持つものです。
特にトヨタの参画は、電気自動車(EV)や自動運転技術の進展を背景に、先端半導体の安定供給が最重要課題となっていることを示しています。
TSMCという世界的リーダーとの連携を通じて、将来的なサプライチェーンの脆弱性を補い、技術革新の加速を狙うものです。
このように、TSMCは日本の主要顧客企業をパートナーに迎えることで、国内での影響力を一層強化し、単なる受託生産の枠を超えて、日本の産業エコシステムの中核を担う存在を目指しています。
投資規模と補助金
第2工場の総投資額は約1兆6,900億円、第1工場と合わせると総額約3兆円に達すると見込まれます。
日本政府も第1工場に最大4,760億円、第2工場に最大7,320億円を補助する方針で、合計最大1兆2,080億円にものぼります。
投資額の約4割を占める巨額の補助金は、半導体を経済安全保障上の重点課題と位置付ける政府の姿勢を示しています。
着工・稼働予定日の公式発表とこれまでの変遷
TSMCは当初、第2工場を2024年末までに着工し、2027年末までの稼働を目指す方針を公式に発表していました。
しかし、その後世間では「着工時期が2025年内に見直された」「稼働時期が2029年上期にずれ込むかもしれない」といったさまざまな情報が飛び交っています。
こうした背景には、TSMC経営陣の発言解釈を巡る地方自治体との見解の違いに加え、技術的課題やサプライチェーン調整、さらには地政学的要因など、複数の要因があるようです。
TSMC熊本工場についての詳細なデータ・分析は地方経済総合研究所(または当研究所)のレポートに掲載しております。
会員の方は「TSMCの概要 ↗ 」をご覧ください。
会員でない方は、「入会のご案内」をご覧ください。
着工延期・中止の報道について

TSMCの董事長(会長)兼最高経営責任者(CEO)である魏哲家(ぎてつか)氏は、株主総会後の記者会見で、熊本第2工場の着工が遅れていることを認め、その理由として「現地の交通事情の悪化」を挙げました。
同氏は、TSMCの進出が「現地の交通に与える影響が非常に大きい」とし、地域住民の不満が高まっているため、このまま進めるのは良くないと判断したと説明しています。
一方、熊本県の木村敬知事は定例会見で「交通渋滞の解消が着工の条件ではない」と明確に否定。工場用地の取得と造成工事が完了しており、建設はいつでも開始できる状況にあるため、「年内着工の方向性に変わりはない」との認識を改めて強調しました。
工場建設と稼働がもたらす複合的影響

経済的影響:経済波及効果、雇用、サプライチェーン
TSMCの進出は、熊本県経済に極めて大きなインパクトを与えています。株式会社九州フィナンシャルグループと地方経済総合研究所の試算では、第2工場を含めた熊本県内への経済波及効果は2022年から2031年までの10年間で約11.2兆円に達し、第1工場単独の試算額(約6.85兆円)を大きく上回ります。
また、第1・第2工場合わせて3,400人以上の高度技術専門職が直接雇用される見込みであり、関連企業の進出による雇用創出も期待されています。
関連記事:TSMC熊本進出が企業投資と地域産業に与える影響〜11.2兆円規模の経済波及効果〜
社会・インフラへの影響:交通、不動産、人材
菊陽町を含む周辺地域では、TSMC関連の通勤者や工事車両の増加により交通渋滞が深刻化しており、県は道路の多車線化や新たなアクセス道路の整備といった対策を急いでいます。
熊本県の地価調査によるとTSMC進出の発表後、不動産市場では、工場周辺の地価、賃貸物件の家賃が上昇しました。特に単身者向け物件では、従業員や建設関係者の需要増から家賃上昇率が熊本市を上回るケースもあります。
さらに、TSMCが提示する高水準の給与は、人材採用の面でも影響を与えており、地元の中小企業は、人材の流出に備え、待遇改善や職場環境の整備といった対策を行なっているところもあります。
| 項目 | 第1工場 | 第2工場 | 両工場合計 |
| 経済波及効果 (10年間) | 約6.85兆円 | 約11.2兆円(第1工場を含む) | 約11.2兆円 |
| 直接雇用者数 | 約1,700人 | 約1,700人 | 3,400人以上 |
環境的影響:水資源と水質汚染
半導体製造には、不純物を徹底的に排除した「超純水」が大量に必要とされます。TSMCが熊本に進出した理由の一つも、豊富な地下水資源にあると言われています。第1工場だけで年間310万トンの地下水を使用しており、第2工場が稼働すればその量はさらに増加すると見込まれています。
この水資源への影響を最小限に抑えるため、熊本県は、事業者に「採取量に見合う量の涵養」を求めるルールを改めました。しかし、産業活動の活発化で水需要が拡大する中、この涵養策が持続可能な水資源管理をどこまで担保できるかは、今後も注視すべき課題です。
さらに、水質面でも懸念が浮上しています。一部報道によると工場からの処理水が放水されている熊本市を流れる川で、半導体製造プロセス(または半導体製造過程)で使用される有機フッ素化合物(PFAS)2種類の濃度の増加が報告されています。現時点では健康被害は確認されず、検出濃度も各国基準を下回っているとされており、熊本県も因果関係について「明確にあるとはいえない」との見解にとどめているものの、こうした状況は、産業発展と環境保全の間に存在する根本的な「トレードオフ」が現れていると考えることもできます。
関連記事:なぜ熊本に半導体工場が集積するのか ― 豊富な地下水と持続可能性の課題
日本の半導体戦略におけるTSMCの位置付けと将来展望
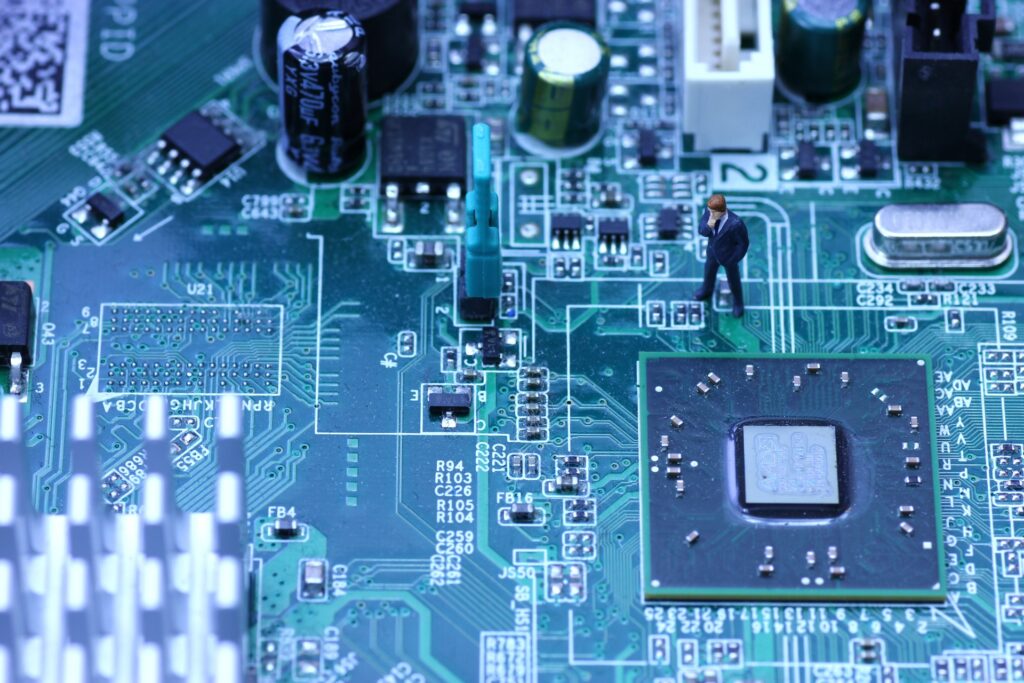
国策としての半導体産業再興とTSMCの役割
TSMCの日本進出は、単なる外資誘致にとどまらず、日本政府が推進する「半導体・デジタル産業戦略」の中核的な取り組みとして位置付けられています。
日本政府の半導体戦略は、TSMC熊本工場と、北海道で次世代2ナノメートル級チップの開発・製造の国産化を目指すRapidus(ラピダス)株式会社の二本柱で進められています。
TSMCが自動車や民生機器向けのレガシーノード(成熟技術)の安定供給を担い、ラピダスが最先端ロジック半導体の開発・量産に挑むことで、日本は国際的な水平分業の中で独自の戦略的位置付けを確立しようとしています。
今後の課題と持続可能な発展に向けて
TSMCの進出を契機とする日本の半導体産業の再興は、単なる工場誘致にとどまらず、産業全体のエコシステムを再構築する試みと言えます。
かつて「シリコンアイランド」と呼ばれた九州の歴史的背景は、今回の動きが一過性のブームではないことを示唆しています。日本の真の強みは、世界シェアの約50%以上を占めるシリコンウエハーや、約90%を担うフォトレジストなどの半導体製造装置・素材産業にあります。
TSMCの進出は、こうした基盤を生かして国内サプライチェーンを再編成するための「呼び水」として重要な意味を持ちます。
しかし、持続的な成功のためには、依然として多くの課題が残されています。深刻化する交通渋滞や住宅不足といったインフラ問題、高待遇を背景にTSMCへ人材が流出する地元企業への対応、さらには水資源の確保や環境汚染への対策が急務です。
これらの課題に包括的に取り組むことができれば、日本はグローバルな半導体競争において、単なる生産拠点を超え、技術革新と環境保全を両立させる戦略的なパートナーとしての地位を確立できるでしょう。
| 項目 | JASM熊本工場 | Rapidus株式会社 |
| 製造拠点 | 熊本県菊陽町 | 北海道千歳市 |
| 生産ノード | 40nm, 22/28nm, 12/16nm, 6/7nm | 2nm |
| 目的 | 車載・民生向けレガシーノードの安定供給 | 最先端ロジック半導体の国産化 |
| 主要な役割 | グローバルサプライチェーンの強靭化 | 次世代半導体技術の確立 |
| 政府支援額 | 最大1兆2,080億円 | 最大1兆8,000億円 |
結論

TSMCの熊本第2工場計画は、日本の半導体産業再興に向けた大きな一歩であり、約11.2兆円の経済波及効果や3,400人以上の雇用創出など、地域と国全体に多大な経済的恩恵をもたらすと期待されています。
日本政府による巨額の補助金を背景に、このプロジェクトは単なる一企業の誘致を超え、地政学的リスクが高まる中でサプライチェーンを強靭化するという国策的使命を担っています。
このプロジェクトの持続的な成功を実現するには、インフラ整備の加速、地域中小企業への支援、人材の確保、水資源・環境への負荷低減といった課題に総合的に取り組む必要があります。
TSMCの進出を、日本の強みである製造装置や素材産業を起点とした「半導体エコシステム再構築」の好機と位置付けることこそが、日本の半導体産業が再び世界で存在感を示すための鍵となるでしょう。
TSMC熊本工場について、レポートに詳細にまとめています。
会員の方は「半導体関連企業の進出と地域経済 ↗ 」をご覧ください。
会員でない方は、「入会のご案内」をご覧ください。